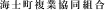海士町に来た経緯
自然ではなく、人に直感したことがきっかけ。
私は水の生き物が好きだったこともあり、都会の水族館で飼育係として働き、また都会の水族館の企画・計画に関わる仕事をしていました。やりがいは感じて働いていたのですが、ふとローカル地域で水族館を企画したくなり、地方移住を考えるようになりました。
しかし地方移住を考えるにあたり、いくつかの地域に実際に訪れたり、移住説明会に参加したりしていたのですが、「良いかも。」と感じる場所はありつつ決断できずに、1年がたってしまいました。
決断できずにいたのは、人の要素でしょうか。私は、移住によるライフスタイル変更を第一にしていたのではなく、地方でやりたいことをやってみたい、というタイプだったので、それができる可能性がある場所をさがしていました。しかしピンとくる場所は、なかなかありません。
それどころか、訪れた先の町の人も「水族館をやりたい」なんていう人間が急に現れてポカンとされる状況でした。そりゃそうだと思いつつも、できる限り話を聞いてもらえる場所を探さなくては…と考えていました。
「もう見つからないし…妥協でそこそこいいと感じた場所にいくか…」と思っていた時に、ボランティアで手伝っていたイベントに、AMU WORKERの雪野さんがゲストスピーカーとして登壇していました。それで少し興味を持ち、AMU WORK説明会に参加しました。
すぐに応募はしませんでしたが、まず海士町に行ってみることは決めました。
行くことに決めたのは、まさに人の印象です。誰が良かったとかではなく、マイペースな人や、ロジカルシンキングをする人、ピュアに物事に取り組む人など、タイプが異なる人が共存しているように見えたからです。
共存できるのは、柔軟な組織設計をつくる視点があるはず。柔軟とは、組織に属する人のフィードバックを聞く環境をもっている可能性が高いはずだ…と勝手に想像を膨らませ、まず遊びに行ってみよう。ということで訪れました。
実際訪れ、やりたいことができる確度はここが高いと考え、海士町に行くことを決めました。
そのあと、面談も行い、まずAMU WORKに入ることを決めました。
これから
まずは海士町や隠岐諸島のことを理解したいし、町になじみたいと思っています。最初に書いた水族館を企画構想するにあたり、海士町の海はどんな海だろうか?町の人は海や自然をどう捉えているのか?観光客はどう感じているのか?といった町とコミュニケーションしながら考えるのが、水族館づくりの面白さと醍醐味だと考えているので、複業を通していろんな職場を見られるのは良いことだと思いました。まずは少しずつ、身をもってして学ぶことと、また町の生活にきちんと根を下ろしていこうと思います。
海士町の海
車の納車が遅れているので、あまり見て回れておりませんが、海士町や隠岐諸島の海の魅力はまだ潜在的に眠っているように思いました。
先日から海を覗いていると、カブトクラゲというクラゲがざっと見ても1000以上は余裕でいるだろうと思うほど大量にいました。このクラゲは、海中ではわかりにくいのですが、水槽下では照明の当て方によってはキラキラと光ります。とても美しいクラゲです。
水産や釣りで親しまれる生物以外の、「よくわからん」海の生物との付き合い方を見つけていくことに、自分の活躍の場があるかもしれないな…と感じています。